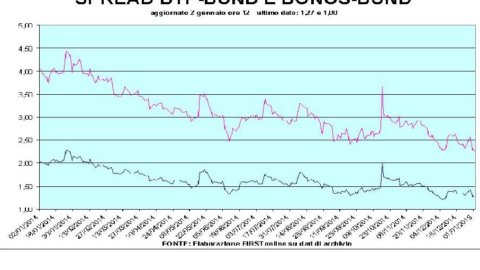ジアンナは鏡台の鏡の前に座り、自分の映りをちらっと見て、中年の女性としては、自分はまったく悪くないと思いました。 しかしその後、彼の視線が彼女の首に落ち、彼女の機嫌はすべて無駄になってしまいました。 枯れていないにしても、彼のリラックスした肌は、彼のXNUMX歳のすべてを表していた。 映画のコメディだけでなく小説の洗練された作家であるノーラ・エフロンが主張したように、首は手とともに女性の年齢を冷酷に探知するものである
ニューヨークの作家はちょうど次のタイトルの小冊子を出版したところだった 首がおかしくなってしまう。 女性であることの苦しみと至福。 ジアナはそれを読んでいませんでしたが、雑誌でノーラ・エフロンのインタビューを読んだことがありました。 著者は、必要な「メンテナンス」には週に XNUMX 時間が必要だと、ある意味何気なく宣言しました。これは、数キロ走行した車の場合と同じです。
ジアナは、自分の世話に費やす時間を頭の中で計算し始めました。 XNUMX時間になると――こんなに時間がかかるとは思っていなかった――彼女はイライラしたように肩をすくめ、「なんてばかばかしいことだ!」とつぶやいた。 ファンデーションを塗る前に、顔と首にクリームを伸ばすことが重要な作業です。 同時に彼女はベッドの上に広げられたシフォンのドレスに目をやった。パステルカラーの目に見えない小さなドレスで、彼女にとっては大金がかかったが、彼女にぴったりだった。
試着時に店員さんに「女の子っぽいですね」と言われたそうです。
もちろん! 彼女は年をとることを拒否した世代で、平均寿命が延びたためか、両親の時代に比べて生活水準が向上したためか、彼女の年齢の女性は少女のように見えるだけでなく、まだ希望を持っていた。 料理。 それが彼の場合ではなかった。 彼女は結婚しており、XNUMX年間結婚しており、スカイで放送されているあの陽気なフィクションのような「死が二人を分かつまで」シリーズの結婚という点ではトログロダイトでした。
「あなたはまだ公海にいるのですね」ファビオは寝室のドアの外を眺めながら考えた。
「時間はあるよね?」 彼はぼんやりと答えた。
「最近、準備にずっと時間を費やしているね」と夫はすでに髭を剃り、服を着て、香水を付けていたと述べた。 ほぼXNUMX歳の素晴らしい体型。 彼女はXNUMX歳の頃と同じようにせっかちで機敏で、車のキーを手に廊下を歩きながら彼女を待っていた。 その間、彼女は、自分の速度がどんどん遅くなっていることに気づきました。
「ガソリンを入れてくるよ」と彼は彼女に告げた。
ジャンナはそのアイデアに感謝しました。 少なくとも、彼女はしばらく彼をそばに置くことはないだろう。
マスカラをなでながら、彼女は今日自分を待っていることについて考えずにはいられませんでした。それは、恐ろしいほどの距離で続いたXNUMX件の葬儀の後の結婚式でした。 彼女は迷信深いわけではなかったが、その数か月間、正確には半年の間に、彼女はかなり理性的な正気を失い始め、それらの奇妙な偶然のことを病的に引きずっていた。 その瞬間まで、彼は死についてよく知らなかったし、それについてあまり考えたこともなく、遠い可能性として頭の片隅に追いやっていた。 彼女の両親は高齢ではあるが適度に健康で、彼女が子供の頃に亡くなった祖父母を除けば、彼女はいかなる悲しみも感じなかった。
すべては、XNUMX 月の雨の最も曇った日に、幼なじみのルシアナからの電話から始まりました。 いくつかの歓談の後、彼は彼女に、最初のボーイフレンドであるダリオが死んだことを告げた。 ジアンナは非常にショックを受けていたため、その時はこの矛盾を理解できませんでした。 つまり、かつて彼を彼女から連れ去り、彼女に恐ろしい知らせを伝えた張本人だったのだ。
「お葬式はいつですか?」 当然のことながら、彼は自分がどのように死んだのかを尋ねる前にさえ尋ねました。 彼女は葬儀の儀式、その雰囲気、会葬者、そして、ドレスアップしたマネキンのように展示された遺体さえも恐怖に感じた。
「まだわかりません。自殺の場合は長い時間がかかります。」
"自殺?" 彼女は馬鹿みたいに答えた。
「ダリオは車の中に閉じ込められて、一酸化炭素で自殺したんです」とルシアナは率直に、しかし最低限の配慮もせずに彼女に告げた。
「でも彼はそんなことをするタイプじゃなかった!」 彼は叫びました。
"知っている。 表面的で無責任な人でしたが、前向きな人でした。 結局のところ、人は変わります」とルシアナはコメントしました。
「彼がなぜそんなことをしたのか知っていますか?」 ジアンナは、暗くて不幸なラブストーリーを想像して尋ねました。
ルシアナは、ダリオが最近ギャンブルにハマって金貸しに多額の借金をしていると兄から聞いたと打ち明けた。 おそらくそれが原因でした。
「信じられない」と彼女はますます混乱してつぶやいた。
"私でもない。 そして昨日から私は彼のこと、私たちがどうだったかについて考えています」とルシアナは結論づけた。
電話の後にジアンナがとったのはまさにそれだった。 過去へ、「かつての私たち」への飛躍:世界を変えることを夢見ていたが、少なくとも自分たちが住んでいた地方都市の現実においては、彼らが語っていた普遍的な愛よりもロマンチックな愛を優先した世代。多くの。
ダリオはある夏の午後、友人の一団の中に現れた。 金髪で、下品なまでに特徴のある顔立ちの彼は、タイトな黄土色のズボン、日焼けした胸元に開いた黒いレースのシャツ、そしてミック・ジャガーのような唇ですぐに注目を集めました。 彼女が最初の言葉を発するとすぐに、幼稚だが恥ずかしい吃音を見せ、彼女のセクシーなイメージは大幅に減少した。 どうやら彼は気にしていないようで、誰かが彼がどもる理由を尋ねると、彼は謎めいた子供時代のトラウマを持ち出しましたが、その詳細については明かしていませんでした。 うわさ話者たちは、おそらく彼が嫉妬していた兄弟が生まれた後に吃音をするようになったのではないかと主張した。 それほど神秘的でも魅力的なものでもありませんが、ほぼすべての子供たちに影響を与えた感情的な問題に対する些細な反応に過ぎません。 いずれにせよ、そのハンディキャップとそれに伴う脆弱性は、部分的には生まれつき、部分的には構築された彼の官能性とほぼ同じくらい少女たちを虜にした。
ジアンナは最初の瞬間から彼に恋に落ち、ダリオは、女性の波動が現れる前からそのアンテナが女性の波動を拾っていた。ある晩、家の下の庭で二人で過ごしていたとき、彼女のすべてを興奮させるようなキスをした。 しかし、たとえそのキスがジアナにとって、かろうじて発音できた言葉よりもはるかに大きな意味を持っていたとしても、彼は彼女にガールフレンドになってくれるようにとは頼みませんでした。 そして彼女は、キャンバスを持たないペネロペのように、彼が庭に現れて誘ってくれたり、ただ注意してくれるのを待っていることに気づきました。 ダリオは経験豊富なプレイボーイのような無頓着さで友達から別へと渡り歩いていたので、当然の結論ではありませんでした。 結局、彼女と彼女の友人であり敵であるルシアナだけがトロフィーを争うために残った。
ジアナは二人の間の確執がどのように始まったのか覚えていなかった。考えてみれば、ジアナが石鹸と水の女の子であるのに対し、ルシアナはミニスカートのような誇張された化粧をしており、見た目がそれ以外にきっかけさえなかった。バンドを探しているグルーピーのように。
結局、ダリオは誰にも不快感を与えないように、両者を平等に分け合い、ジアナとは良い子の役を、ルシアナとは好感の持てる悪役を演じることになった。 しかし、ダリオのキスがあまりにも上手だったので、彼女には彼に最後通告をしたり、別れたりする力がありませんでした。 彼女はまた、彼女によれば、ますます短くなったスカートとサイハイブーツを履いた、見た目だけで中身のない敵の友人を、何とかして倒したいと願っていた。
ずっと後になって、彼女はこの二人がお互いのために作られたものであり、ダリオの強い官能的な衝動は動物の本能の産物であり、その背後には何も存在しないことに気づきました。 しかし、XNUMX歳のとき、彼が自分の感情と混乱したときのホルモンを測定する基準はまったく異なっていました。 彼は彼女を危険にさらし続けたにもかかわらず、あるいはおそらくまさにそのために、ダリオは彼女の考えと心を本能的に占めたので、彼女が恋に落ちた少年ファビオに対してさえ、これほど激しい感情を二度と感じることはなかったでしょう。 XNUMX歳で結婚することになった。 の日記のページを埋めました。 ねぎ、にんにくなど 自分の名前を書きながら、彼は素朴な詩を詠んだ プレヴェール 彼は誰にも読ませるつもりはなく、愛する人の写真も持っていなかったため、雑誌から切り取ってミック・ジャガーのスナップショットをすべて貼り付けた。 彼は聞いていた 女性の陰部 ローリング・ストーンズのメンバーは、ロック・スターの代わりにダリオがあの低くセクシーな声で彼女のためだけに歌っていることを夢見ていた。 彼女が歌うとき、吃音することはなかったし、結局のところ、ジェーンとジアナの間に大きな違いはありませんでした。
それからXNUMX年間、彼女はルシアナとともに何度もため息をつき、少し涙を流しながらそのロープに飛び乗り、その中に彼が彼女に捧げた忘れられない瞬間が散りばめられていた。 なぜなら、彼女と一緒にいたとき、ダリオは彼女の不満や不安に報いてくれたからです。 彼は、優しく、保護的になる方法を知っており、結局、まだ性的自由に取って代わられていなかった常套句のように、彼女を尊敬していました。
そこで、彼を征服し、ライバルを決定的に弱体化させるために、ジアナは唯一の貴重なカード、つまり処女のカードを切ることにしました。 ある日の午後、ダリオは熱を出し、家に誰もいなかったので、隣のベッドで丸くなっていました。 すぐに彼女は彼の熱狂的な抱擁に圧倒され、震え始め、今度は燃え上がり始めたので、彼が感染したウイルスが即座に彼女に感染したのではないかという疑念が彼女の中に閃いた。 それは部分的には真実だったが、ウイルスはインフルエンザではなく、夢中、あるいはジアンナが信じていたように愛と呼ばれる病気だったということだけだった。
ダリオが彼女の服を脱ぎ始めたので、ジャンナは彼に脱がせました。 もしある時点で彼が咳き込む発作に襲われていなければ、彼女はその後も抵抗しなかっただろう。 明らかに、彼が咳をし、水を飲み、錠剤を飲むのにかかった時間も、彼が状況を評価し、このままではいけないと決断するのに役立った。
ようやく咳が止まると、ジアンナは中断したところから再開し、彼女ができる限りの無邪気な官能性を注ぎ込んだ。 しかし、彼はこう言って彼女を止めた。 それから彼は再び彼女に甘くて刺激的なキスをし始め、それが彼女を軌道上に送り込んだのに、彼女をそこに残して混乱して宇宙をさまよったのです。
それ以来、彼らは二度と一人になることはありませんでした。 そしてXNUMXか月後、一派全員が出席する多くのパーティーのXNUMXつで、ダリオは彼女を一瞥も惜しまず、ルシアナと縛られて踊り続け、彼女の心は傷つきました。 彼女は被害者意識に熱心ではなかったので、その友人グループから離れて、もっと新しくて気の合う他の仲間を求めました。
その後、彼女はファビオという少年に会いました。彼はダリオよりも間違いなく知的で刺激的な少年でした。 彼女の視野は家の下の庭や最近の征服に限定されず、世界を探索したいという彼女の好奇心と願望に巻き込まれ、さまざまな分野に及んでいました。 一言で言えば、一緒に成長するのに最適な男です。 そして、時々ダリオの夢を見ることがあったとしても、目が覚めたとき、彼女はうまく逃げられたという安堵感とともに懐かしさを追い払いました。
時間が経つにつれ、その庭園は集会の場ではなくなりましたが、夏になると彼女は市内の入浴施設でダリオに偶然遭遇し、そこで昼食を食べに行くことがよくありました。 数年間、彼女は彼が後に彼の妻となる美しいブルネット、そして幼い子供たち、男の子と女の子と一緒にいるのを見ていた。 彼らは幸せな家族のように見えましたが、ダリオは父親の家族の役割にある種の焦りを隠すことができませんでした。
XNUMX歳になった今でも、彼はまだ少年の頃と同じ体格を持っていたが、若さによってかつては和らげられた下品さが顔の特徴に完全に現れていたとしても。 それ以外の場合、彼はいつも自分と同じでした。 彼は好きな女性の前にいると、妻がいるにもかかわらず列に並んで獲物の匂いを嗅ぎ始めました。
そのXNUMX月の日、ジアンナさんはタオルの上で体を伸ばして眠りに就こうとしていたとき、太陽が突然暗くなりました。 彼は目を開けると目の前に彼を見つけました。
「なぜ一人で?」 彼は彼女に尋ねた。
"あなたも?" 彼女はブルネットや、もう成人しているはずの子供たちの姿を見ることなく、質問を彼に向けた。
「私は一人ではありません、私は自由です。 違います。"
ジアンナは起き上がって、彼にもっとよく説明してほしいと頼んだ。 ダリオは彼女の隣に座り、妻と別れるつもりだと彼女に告げた。
「ごめんなさい」とジアナは答えた。
「私は結婚に向いていない」と彼は指摘していた。 それから彼は彼女の目を見て、何年も彼女に寛大だったかを熱心にささやきました。 彼女は少女の頃よりも今の方がずっと美しかった。
ジアンナは一瞬、XNUMX年前に戻ったような軽い震えを感じた。 ダリオはレーダーを常に備え、わずかなチャンスを捉える準備ができており、すぐに攻撃を開始しました。 彼は彼女に、長い時間を経て、自分たちが始めたことを終えることができたらどんなに素晴らしいだろうと気づかせた。 彼は時々それについて考えたことがありました。 彼女ではないですか?
ジアンナは幸せな結婚生活を送っており、夫を浮気するつもりはないと彼に話した。
「ああ、みんなそう言うんだよ」と彼はいたずらっぽく答えた。
結局、彼女を反応させたのは彼の傲慢さだった。 「まあ、私はそうではありません すべて もしよろしければ、私は静かに日光浴したいのですが。」
ダリオはその打撃を受け、愛情を込めて彼女の頬を撫でた後、姿を消した。
この頃、彼が彼女に警告していた通り、彼はXNUMX代の子供XNUMX人を預けていた妻と別れ、自分より年下の女の子から別の女の子へと行き来し始めていた。 当然のことながら、彼女に知らせたのはルシアナであり、二人が会うたびに、彼女は共通の失恋について最新情報を彼女に伝えた。 ある日、彼は「ガールフレンドの年齢は自分の年齢に反比例しており、ばかげているところだ」とコメントした。
ジアンナさんは自殺の数カ月前にダウンタウンの店で彼を見かけていた。 彼の顔は酒を飲んでいるか何かをしているかのように重く見えたが、体は常に痩せていた。 彼はスキニージーンズの上にロッカーレザージャケットを着ていました。 口はまだミック・ジャガーのものだったが、しわはキース・リチャーズに似ていた。 「XNUMX つのローリング ストーンが XNUMX つになった」と彼は挨拶しながら考えました。
彼らはあれこれと少し話していましたが、ある時点で、それまで洋服を眺めるのに忙しかった女の子が近づいてきました。 彼女は彼の腕を取り、耳元で何かをささやきました。 彼女は彼の娘になるにはあまりにも愛情深かったが、彼の配偶者になるには十分若かった。 実際、彼は彼女にそのように提示しました。 彼は二十、二十二歳を超えていなかっただろう。
ジアンナさんはXNUMX種類の抗不安薬を飲みながらようやく参列した葬儀に、ジアナさんの姿はなかった。 その代わりに、彼の両親と兄弟のほかに、彼の妻と子供たち、彼らの古い友人、そして彼の知らない多くの人たちがいました。
そしてもちろんルシアナも。
彼らは両親にお悔やみの言葉を伝え、棺の中のマネキンに最後の別れを告げた後、ずっと心を閉ざしていた。 XNUMX年代のゴシック映画にふさわしいビジョン。 彼らはダリオにダークグレーのスーツを着せたが、これはダリオが結婚式の日にも着ていないもので、白いチュニックと黒いズボンを好んでいた。 ルシアナはそのことを彼に明かし、その時初めて彼は彼女の結婚式にボーイフレンドと一緒に出席したことを彼女に話した。
「彼ではない」とジアンナさんは独り言を言い、結婚式に招待されなかったことへの失望をはねのけて、無理に遺体を見つめた。 彼はXNUMX歳で、死に直面する時が来た。 灰色の顔と硬い顔立ちをしたその男はダリオの模倣であり、ジャンナはあの時ほど、あの儀式や展示の理由を自分自身に問いかけたことはなかった。 彼は自分が古くからある深い宗教的伝統を扱っていることを認識しながらも、それはいくぶん野蛮で無意味な実践であるという確信を強めていました。 彼は、親族に遺体をさらすことがどれほどの慰めとなるのか理解していなかった。 ジャンナは、死後の魂の生存を信じ、肉体を離れて別の次元、つまり平和、光、静けさの次元に移す神聖で微妙なエネルギーを信じていました。 しかし、彼女は理性があったため、従来の意味で神を信じることができませんでした。 そのため、彼女は自分自身を信仰を求めている人間だと考えており、信仰に口づけされた人たちを羨ましく思うこともありました。
ダリオは確かにそのような人物ではありませんでした。 彼が人生に終止符を打つ決意をするためにどのような暗闇に陥ったのか、そして最後の瞬間に彼の心に何が起こっていたのかは誰にも分かりません。 それは勇気ある行動だったのか、それとも卑怯な行為だったのか? ダリオと彼の人生への愛を知っていたのは間違いなく彼が最初でした。 そう思うと、彼女は泣きそうになった。
「もったいない!」 新鮮な空気を吸いたくて礼拝堂を出ながら、彼女はそう思った。
「大丈夫ですか?」 ルシアナは彼女に手を差し伸べながら尋ねた。
「はい、そうですね」ジアナは「このすべての意味を考えていたのですが、つまり、人生で最初に見た死人がダリオだというのは奇妙に思われませんか?」と答えました。
ルシアナは、これまで特に感受性や神秘性が高かったわけではないが、正気を失ったかのように彼女を見つめた。 彼は首を振って「もうすぐ礼拝が始まります」と答えた。
教会では、お香の煙で気を失うのではないかと心配しながら、ジャンナは長い間その疑問について考えていました。 それはもしかしたら運命の兆しだったのでしょうか? もしそうなら、彼はそれを理解できませんでした。 しかし、その後に続いた厳粛な儀式は、理性的な考えを手放し、自分自身を、心も精神も神秘に捧げなければならない瞬間があることを彼女に理解させました。
それはその瞬間の一つでした。
彼は祈りに加わり、その雰囲気に身を任せ、全体としてはある種の安らぎを感じた。
その後、ルシアナと一緒に棺に入った後、彼女はついに自分の青春時代に別れを告げようとしていることに気づきました。 実年齢に比べて長い期間が続いた。
次の日から、彼女は仕事、家族、たくさんの約束などいつもの生活に戻りましたが、何かが足りないように感じ、いつもと違うと感じました。 彼女はその感情をどう解釈してよいのかわからなかったので、足の小指が欠けているなどの身体障害があるのではないかと考えました。 深刻なことや不自由なことは何もなく、ただ迷惑なだけで、時折人生の短さや夢の終わりを思い出させる痛みがあった。 しかし、日が経ち、日常に戻るにつれて、ダリオと死のことを忘れ始めました。
ある朝までは…電話が鳴ったとき、彼女はオフィスに入ったばかりでした。 彼女は電話に出たが、好奇心よりもイライラしていた。 彼女はよく言っていたように、早朝、夜明けに電話してくる人々を憎んでいました。
「ジャンナ…」
彼が彼女の名前を言った後、聞き覚えのある男性的な声が小さくなった。
"最大?" 彼女は曖昧に答えた。
マッシモは話し始め、同時に混乱した音を立てて泣き始めた。 ジアンナがどんなに理解していても、彼女は決して起こり得るとは思っていなかった何かを理解していました。 彼女はオフィスの椅子に仰け反り、受話器を手に、頭から血が流れ出し、すべてが彼女の周りで回転しました。 今、彼には何も見えず、真っ暗闇だけが見え、そこから二度と現れないことを望んでいた。
しかし、それは現れました。 誰かが彼女の心臓を引き裂き、それを吐き出す前にまだ噛んでいるような感覚で。
彼女はカバンを掴み、呆然と彼女を見ていた同僚のマリーナに、「行かなければいけない」と言わせ、誤解を望んで病院に急いだ、そう願っていた…
救急治療室の待合室で肘掛け椅子に倒れ込むマッシモさんと、その隣で必死に泣いているジュリアーナさんの母親ファウスタさんを見たとき、彼女はもう希望はないと悟った。
彼女の親友であり、彼女の分身であり、彼女自身の最良の部分であるジュリアナは、永遠に去ってしまいました。 それ以来、そしてその後も、ジアンナはジュリアナのことを決して死ではなく旅立ちと結びつけるようになり、ジュリアナのことを語るときはいつも「彼女は去ってしまった」という言葉を口にした。
彼女は驚いて涙も出ず、マッシモ、次にファウスタを抱きしめ、彼らの隣に座り、家族を中に入れる前に友人の体を元に戻すのを待った。
そのベンチで彼女は、現在や一緒にいた人々から自分自身を遠ざけ、完全に空虚な瞬間を経験しました。 彼女を包む暗闇から夫の思いが浮かび上がり、彼女が彼に電話する力を見つけるまでは。 ファビオはすぐに到着し、黙って彼女を抱きしめた。ジアンナは自分の強さと堅実さ、足下で崩壊しつつある世界の固定点を感じ、認識した。
「でも、どうしてそうなったの?」 教会。
ジアンナは混乱して彼を見つめ、彼女の目には涙があふれ、彼らを手放す決断ができなかった。
ファビオを抱きしめた後、マッシモは元気を取り戻したようだった。「今朝、彼女を起こすことができなかった。睡眠薬を飲んだのかと思った。彼女は最近不眠症に苦しんでいる。 私は彼女を揺さぶりましたが、彼女は答えませんでした、そして…医師たちは、彼女はおそらくすでに昏睡状態にあると言いました。」 彼は断片的に文章を終えたが、それでも何が起こったのかについてかなり完全な全体像を提供することに成功した。 最初の性急な診断によると、右側が完全に麻痺しており、口がしかめっ面になっていることから、脳卒中を起こしている可能性があるという。
「彼は高血圧やその他の危険な病気にはかかっていませんでした」とジアナさんはつぶやいた。 そして、親友が残したものに直面したとき、彼女は罪悪感を募らせながらも、そう自分に言い聞かせ続けた。 それは単に、彼女が苦しみにもかかわらず生きていたという事実によるものである。
彼女はファビオと一緒に入ったが、足はゼリー状になり、体中が震えていた。 夫が彼女の手を温かく慰めながら握ると、ゆっくりと心拍数が下がり、足の震えが止まりました。 しかし、彼女以上に死に対して頑固な態度をとった彼は、ある時点から彼女を残して姿を消してしまった。
"あなたは私にこれを行うことができますか?" ジャンナはその瞬間、部屋の中にジュリアナの存在に気づいた。 シーツに包まれた硬い体とも、嘲笑するようなしかめっ面とも無縁の存在。
「まあ、今回は本当にめちゃくちゃだったね」マッシモとファウスタが二人を放っておこうと出かけたのに気づいた彼女は言った。 どちらかの家にいて、部屋に入る人は誰でも侵入者とみなされていたときのように。
ジュリアナの声が聞こえたという感覚が強くなり、彼女はこう続けた。「あなたはいつも敏感すぎて、あまりにも傷つきやすいので、魂に深い溝を刻んだ人生の傷を無傷で通り抜けることができませんでした。 あなたを襲った大きな痛みを乗り越えたと思っていましたが、そうではありませんでした。」
高校時代からの友人である彼らは、友情のおかげで精神分析医のソファから救われたとよく主張していた。 彼らはいつもお互いに、最も親密な考えから夢に至るまで、すべてを話し合っていました。 ジュリアナさんが妊娠XNUMXカ月で妊娠していた子供を亡くしたとき、ジアナさんは母親になれないというひどい痛みを和らげるために、あらゆる方法でジュリアナさんに寄り添い、慰めようとした。 彼女に養子を迎えるようアドバイスした。 しかし、マッシモはそのことを聞きたくなかったし、養子縁組は非常に困難でイライラする道だった。 母親になることに専念してきた彼女は、母親になれないことを宣告されていた。 しかし時間が経つにつれて、彼は運命と折り合いをつけたように見えた。 彼女は立ち直ったが、明らかに彼女の中で何かが切れて、痛みの塊が時限爆弾のように彼女の体の周りをさまよい、それが爆発するまで続いた。
ジアナは友人のためにできる限りのことをしたのかと疑問に思いましたが、「はい」と答えました。 彼は心から彼女を愛し、彼女が悲しいときは笑わせ、彼女が心から望んでいた子供の代わりを彼女に提供し、名前だけでなく実際には彼の一人娘であるカミラの叔母の名前を挙げました。
ジュリアナとダリオはお互いのことをほとんど知りませんでしたが、彼らはジアナが思春期の段階を交互に歩んできた XNUMX つの並行世界に属していました。 衝突はしなかったものの、少し離れたところで崩壊した XNUMX つの世界は、彼女の青春に終止符を打ち、彼女の心に大きな空白を残した。
メイクを終えてドレスを着ているときに、ファビオの声が彼女の記憶に侵入した。
「式典が始まるまであとXNUMX分だ」と彼は彼女に念を押した。
「準備はできています」とジアナは答えた。 彼女は、人生の第 XNUMX 部分、つまり、そこに到達すれば老年期に至る移行期に直面する準備ができていました。
ジュリアナの失踪により、それまでは漠然としか感じていなかった明日の不確実性が、彼の頭の中に常に存在するようになった。 マッシモが棺を閉じることにしたため、少なくとも遺体への敬意を払うことは免れたが、友人の葬儀後、彼女は「XNUMXがなければXNUMXはない」という強迫観念に襲われた。 彼女が生き続ける特権を自分自身に保証するために、ダリオとジュリアナ以上に何を持っていたでしょうか? 確かに、ダリオは自分自身の目的の設計者でしたが、ジュリアナには選択の余地がありませんでした。 しかし、ジアナさんにはそれが本当にそうなのか確信が持てませんでした。 どちらも、形は異なるものの、魂の死という同じ深刻な病理に影響を受けていました。
すべての説明を求めようとする彼女の熱意が呪われ、その結果、彼女は暗闇と同じくらい広大で、ある意味で非常に悲惨な迷宮に足を踏み入れることになった。 つまり、私たち一人ひとりが自分の生と死に責任があるということです。 いずれにせよ、一つだけ確かなことは、彼女はどうしても生きたかったということだ。 彼は人生のすべて、老いと死を除くすべてを愛していました。
しかし、今度は自分の番かもしれないという仮説が彼女の中に非常に緊張を生み、彼女は年老いた忌まわしい貴婦人の訪問に備えて霊的に準備を始めたが、それは彼女のバランスにかなり深刻な結果をもたらした。 彼女は食べず、眠らず、ばねのように緊張しており、ファビオを筆頭に誰に対してもひどい態度をとっていた。
そして、夫が自分より先に亡くなっていたかもしれないという耐えがたい考えが妄想に浮かんだとき、彼女は老年は死よりも悲劇ではないことに気づき、それを呼び起こすことを決心しました。 しかし、もし選べるなら、彼より先に去りたかったと思い、彼女は死の床でファビオが隣にいて手を握っている自分の姿を想像した。
偶然か運命か、風の強いXNUMX月の朝、彼の苦しみに終止符が打たれた。
再びそのニュースは電話で彼女に伝えられましたが、彼女はこの偶然の一致を単にテクノロジーのせいだと考えました。
「ジアナ、最愛の人、この知らせを伝えてごめんなさい。 オッタヴィオおじさんは死んだ」と母親の妹リンダが彼女に告げた。
"ときにどのように? で、ママは知ってるの?」 彼女は彼女の中に広がっていた安堵感を裏切らないように、息を切らした。
リンダおばさんは、最初に彼女に話した方がよかったと彼女に言いました。 それから彼女は、その朝、いつものように焼きたてのパンと新聞を届けに兄の家に行ったと話しました。 彼女は電話をしましたが、彼は彼女のために電話を切りませんでした。 つまり、彼女は寝ていると思って鍵を使って入ったのです。 彼は前の晩にそれを聞いていました、そして彼は大丈夫でした。
「彼はベッドにいて、眠っているように見えましたが、眠っていませんでした」と彼女は途切れ途切れの声で続けた。 「とにかく、彼は眠ったまま穏やかに息を引き取りました。」
母親の兄弟の長男であるオッタヴィオ叔父さんはXNUMX歳で、充実した豊かな人生を送り、正気を保っていた人であれば誰もがそう思うであろう死に方をした。
しかし、最も重要なこと、そして彼女の悲しみがなければ彼女を飛び跳ねさせたであろうことは、シリーズのXNUMX番目である彼の死がその倒錯的な連鎖を閉じたということでした。
「なぜそんなに思慮深いのですか?」 ファビオは彼女に尋ねた。
彼らは車に乗っていて、式典が行われる教会の近くに到着する時間が近づいていました。
ジアナさんは夫と握手し、「私は思慮深いわけではありません。幸せです」と答えた。
「たとえカミラが結婚したとしてもね」と彼は冗談を言った。
「ああ、気にしないよ」と彼は答えた。 そして彼は状況の奇妙さを考えずにはいられなかった。 彼の娘は XNUMX 歳で、結婚することなど彼にはまったく考えていませんでした。 今日のすべての若者と同じように、彼には他のプロジェクトや他の優先事項がありました。 何よりも、そのキャリアは、カミラの場合、著名な地位や権力の地位に就くことを目的としたものではなく、衣装デザイナーという彼女が大好きな仕事をすることを目的としたものでした。 彼は DAMS に出席し、優秀な成績で卒業し、今まさにローマへ向かい、そこで映画とテレビの世界への第一歩を踏み出そうとしていました。
教会の前の草が生い茂った空き地で身振り手振りをする彼女を見たとき、ジュリアナさんの言葉が彼女の心に甦った。「カミラは地球上で最も消えた生き物だ。 しかし、真実でもあります。」 そうです、彼女の娘は、本物で、寛大で、誠実で、率直に物を言う女性でした。 ジアナは、それらの性質が芸術環境において欠陥にならないことを望んでいた。
カミラとジュリアナはお互いをとても愛していました。 おそらく、彼らは残忍さを犠牲にして、真実への同じ愛をお互いに認めていたからでしょう。 一方、ジアナはより外交的で、あまり大胆ではなく、常に複数の視点から状況を観察しようとしていました。 ジアナさんは、恐ろしい知らせを告げられたカミラさんの絶望的で悲痛な涙を決して忘れることができませんでした。 彼らは耐え難い痛みに対して盾を形成するためにしっかりと抱き合い、これまでにないほど一体感を感じさせました。
彼女は娘のドレスの裾がほどけ、足に糸がぶら下がっていることにすぐに気づきました。 彼女がドレスや衣装のファンだったという事実は、彼女をだらしなさから守ることはできませんでした。 実際、カミラは自分の服装についてはほとんど、あるいはまったく気にしていませんでした。それは、自分の健康を無視する医師のようなものでした。
二人はキスして抱き合い、その後、ジアナは機転を利かせて、事故を解決するよう彼女にアドバイスした。
カミラさんは自分の車に乗り込み、ヴィンテージと言えるほど古い小さな車に、商売道具を入れて仕事に取り掛かりました。 ジアナさんはスカートの生地の上を機敏に動く娘の器用な手を目で追い、その器用さは誰から得たものなのか不思議に思った。 彼女はかろうじてボタンを縫い付けることができました。
彼女が顔を上げると、ちょうど娘の車とは異なり、年代物と思われるすべての番号を備えた白い車が到着するのが見えました。 車は教会の庭の前に止まり、しばらくして花嫁が降りました。
ジアンナは息を呑んだ:彼女は美しかった! 彼は威厳に満ちた立ち振る舞いをしており、彼が放つ光は彼のプラチナブロンドの髪とは何の関係もなかった。その髪は明るい色のつばの広い帽子からはみ出していた。 ジアンナさんは、そのドレスさえ完璧だと思ったが、それは人生で初めて結婚するという、老いに逆らう勇気を持ったXNUMX歳の女性が、ベージュの水玉模様の茶色のドレスを着ていたからだ。 膝丈のドレスにはベージュのサッシュと、胸元に留められた同色のシルクのバラが添えられていました。 花嫁はお揃いのハイヒールのサテン靴を履き、手には同じ色のリボンが付いた黄色いバラの花束を持っていました。
彼女を通路に連れて行こうと腕を伸ばした男性は、見覚えのある顔立ちをしたXNUMX代の男性で、少しかがんでいてもまだ元気だった。
リンダおばさんは微笑んでそれを握りました。
父親が一緒に教会に向かって進み、母親が親戚の行列に先駆けて安全な距離を置いて後を追っていくのを見て、ジアンナの目は感情で満たされた。
その後、すべてが終わり、涙と喜びと笑顔が溢れると、ゲストたちは昼食のため高級ホテルに移動しました。昼食は夕方、おそらくは明け方まで続きました。
最高の伝統としてオーケストラもありました。 リンダおばさんと夫のカルロはダンスが好きだったからです。 実は彼らはダンスクラスで出会い、恋に落ちたのです。
このパーティーは本当に家族にとって長い間記憶に残るものでした。 まず第一に、配偶者の年齢について、彼女はXNUMX歳、彼はXNUMX歳であるが、これはかなりの物議を醸した事実である。 そして、一生結婚しないと誓い続けたリンダおばさんのセンセーショナルな降伏に対しても。
「結婚は自然に反する行為だ」と彼はよくアルゼンチン人らしい笑い声を出しながら言っていたが、ある日、彼は彼女にこう言った。「昔は違った。 戦争の間、出産での死、そしてさまざまな病気の間で、それは長く続かない運命にありました。 さらに、当時の会社は代替手段を認めていませんでした。 もし結婚していなかったら、あなたは未婚の女性で、孫か老人の乳を育てることだけが得意でした。 ある種の儀礼がもはや守られない時代に生まれたことを天に感謝します」と彼女はひるむことなく続けた。
ジアンナは、子供の頃から服や化粧、そして何千もの女性の技巧の魅力的な世界を彼女に教えてくれた、少し風変わりな叔母のことがとても好きでした。 彼の家は神秘的で魅力的な場所で、あらゆる物体がエキゾチックな場所から来たものであり、あらゆる部屋から不穏な香りが漂っていました。
リンダは自由で完全に独立した女性で、常に仕事をし、旅行し、たくさんのことを愛してきました。 彼はオッタヴィオ叔父さんによく似ていたが、美しく大勢の家族を育てたという点が異なっていた。 でも、男のほうが楽だった、とリンダおばさんはいつも主張していた。 「男の後ろには必ず女がいるが、女の後ろに男はなかなか見つからない」というのが彼の格言の一つだった。 ですから、彼が結婚の意思を発表したとき、ジアンナにとってそれは神話の崩壊でした。
カルロの腕の中で軽くくるくると回っている今の彼女を見て、彼女は一か月前の午後、彼の家でコーヒーを飲みながら、リンダ叔母さんがこれまでにないほど心を開いてくれたあの日のことを思い出した。 「恋に落ちた、それだけだ。 それは、年齢を重ねるにつれて、私たちはより壊れやすくなり、安定した愛情を必要とすることになるでしょう。これまで、私には恋人がたくさんいたにもかかわらず、一度も行ったことはありませんが、隣に男性がいる必要性を感じています。 カルロと私には、普通のカップルのように、習慣になったり、無関心になったり、さらに悪いことに、お互いを憎んでいることに気づく時間はありません。」
「必ずしも時間の問題ではありません」とジアナさんは言う。「新婚旅行の後にお互いを憎み始めるカップルもいます。」
「わかっています、わかっていますが、おわかりのように、私はその可能性を恐れないほど賢いと思っています。そして、いずれにせよ後悔はしません。」
それから、まるで重大な秘密を明かすかのように、彼はこうささやいた。「カルロは私より若いので、私の日が来たら、彼が最後まで私のそばにいてくれると願っています。」
リンダおばさん、よくやったね、あまり浸漬せずに問題を解決してくれたリンダおばさんのダンスを見ながら、ジアンナは思った。
ダンスを始めたリンダおばさんとカルロおばさん、彼はXNUMX歳、彼女はXNUMX歳の父と母も加わり、優雅な、ほとんど共生するような動きをした。 結婚してほぼXNUMX年が経ち、口論や嫌な思いはあったものの、二人はしっかりとした模範的な存在でした。
徐々にゲスト全員がダンスフロアになだれ込み、その目は飲んだばかりの飲み物だけでなく、パーティーを祝う喜びにも輝いていました。 彼らはあたかも明日などないかのように、年齢と病気にもかかわらず、まだ人生のすべてが待っているかのように、のんきに踊った。
その結婚の特殊性を考えると、ダンサーの平均年齢は約XNUMX歳で、カミラとどこから来たのか分からない若い男性を含む唯一の若者は場違いに見えました。
「このダンスを私に許してくれませんか?」 ファビオは手を差し出して彼女を誘った。
ジアンナは立ち上がって夫の後を追った。
彼の腕の中で軽くくるくる回りながら、彼女は生と死のパラドックスについて考えずにはいられなかった。 ジュリアナやダリオのような、これから何年も先があるはずの人々が突然去ったという事実について。 結婚など考えたこともなかった娘のような若者たちと、少女のように恋に落ちた健康なXNUMX歳の女性について。 言い換えれば、脇に置いた若者とそれを楽しんだ老人です。
そして彼女は? 彼は次のどのカテゴリーに属していましたか?
オーケストラがワルツを打ち始めると、ダンサーたちは一斉に同じ方向を向いて動き始めました。
ジャンナはファビオの安全な腕の中で流れに従い、足は軽く、頭は回転し、心の中で音楽が流れ、結局それは問題ではなかったと思いました。
彼女にしてみれば、あたかも明日などないかのように、あのワルツの調べに合わせて踊って踊ったことだろう。
ラウラ・スキアヴィーニはトリエステで生まれ、そこで暮らし、働いています。 彼は単行本を出版した 私が欲しいのはU2だけです (Campanotto Editore) を出版しており、いくつかの短編小説の著者でもあります。 彼の小説の中には次のようなものがあります。 運は才能だ (ロビン エディションズ、2007)、 甘いのが好きな人もいます (ニュートン コンプトン、2014)、 すべてはヨガについてです (ニュートン コンプトン、2015)、 心臓が鼓動するところ (ゴーウェア、2018年)。